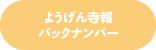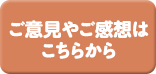開通90年の大城通りの “大城”とは?
大城通りが開通90年を迎える。90年前の昭和3年といえば、池上電鉄が延伸され全線(蒲田―五反田)開通(6月17日)した年でもある。池上駅自体は大正11年10月6日、蒲田―池上間の駅として開業しているが、大正12年9月1日の関東大震災の復興と、それに伴う東京市の拡大という機運の中で、大城通りも開通したといえるだろう。
この大城通りは西蒲田1丁目と6丁目の間を走る多摩堤通りから池上5丁目の池上通りまでをさす。厳密にいえば、西蒲田6丁目の旧・女塚本通りから大森高校のある西蒲田2丁目までだ。しかし、実際のところ「蒲田と池上を結ぶマッツグ(真っ直ぐ)で広い通り」として期待された。
昭和3年の時点では、西蒲田側は東京府荏原郡蒲田町大字女塚であり、池上側は荏原郡池上町大字堤方だった。すなわち、大城通りは旧・女塚村の地域を南北に縦断する道路だった。それでは、“大城”の名称は、どこから生じたのか?
大城通りの中ほどに、昭和4年創業の萩原製畳がある。店の前には、狐が地蔵に化けたことで、可愛い尻尾がちょっぴり覗いた「おおしろ地蔵」がある。同店で話を聞いたが、「マッツグで大きくて広い通り」の「広い」が江戸っ子(東京っ子)の訛りで「シロい」になり「オオシロ」⇒「大城」になったのではないか、という。大城通り商店会でも以前、大城の語源を調べてみたが、わからずじまいだったという。
ところが、『大田区地図集成』を見ると、一〇二~三ページの「第十三図 蒲田町」(蒲田区 其ノ二)の女塚町の字名として「大城」が見える。東京市蒲田区が発足したのは昭和7年10月1日、蒲田村が蒲田町になったのは大正11年10月10日のことだから、その地図はその10年間に作られたものと推測できる。蒲田区や大森区が成立する以前に、女塚には「大城」という字名があったことになる。現在の地図を重ねてみると、相生小学校からマート飯島あたりの大城通りの両側が「大城」ということになる。驚くのは相生小学校の、かつて、そこには女塚神社の女塚霊神に由来する「少将の局」伝説の「局橋」があったが、その東側に「大城」の字名より小さい「本城」という地名が記されていたことだ。
もちろん、女塚には城の遺構や痕跡も見当たらない。『新編武蔵風土記稿』を見ても、そうした小名も出てこない。しかし、女塚地区には五辻とか複雑に曲がった小道(厨子)が今でも多い。その意味では城を彷彿させる。恐らく、幕末頃、新田義興・少将の局の伝説を念頭に、瑞祥名として「大城」を採用したのではあるまいか。