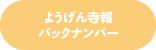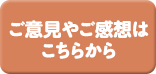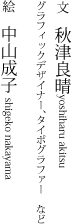
それより数年前、ボクは会社勤めを辞め、フリーと言えば聞こえはいいけれど、その日暮らしの生活が続いていました。友人や、前の勤め先で知り合った印刷屋さんからの細々とした仕事でした。近所の喫茶店で打ち合わせをするのですが、仕事の話ももそこそこに、語ったのは「デザイン」の話ばかり。時間はあっという間に過ぎていました。何かに憑かれたように喋っていたようです。それは、自負するほど世間が認めてくれない事への苛立ちと、明日は仕事がなくなり、食べられなくなるという不安など、叫びたい思いがそうさせたのかも知れません。語りが功を奏してか、仕事は増えていきました。人との出会いも増えていき、そして、アートディレクターという肩書きをもらうまでになっていました。
親戚で法事をするというので母から是非にと言われて帰郷しました。その頃には経済力もついていて、親戚の子らにお小遣いをあげられるようになっていました。おばさんたちに、「あのよっちゃんが」という驚きがあったようです。そして、母の一番下の妹であるおばさんが、「うちに泊まらんね」と言いました。その夜、おばさんの家では、見た目も美しい料理がずらりと並びました。おばさんは旅館でまかないをやっていたのです。談笑しながらの食事は続きました。そして、出された料理の全てを食べ尽くしていました。食後、習い覚えたお経を仏壇に唱え、親戚行脚を終えました。
東京に帰ってから、数日後、母から電話がありました。母は、「何かあったとね?」と聞きました。親戚中で「よっちゃんは変わったねえ」と評判だと言うのです。「うちは、鼻が高かったばい」と母は言いました。一つだけ親孝行ができたと思いました。
(ようげん寺報 2017年12月15日発行 第12巻 第6号掲載)